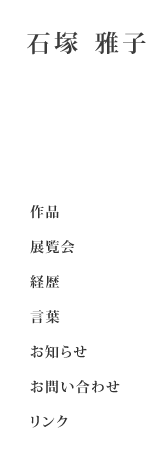■
美しい法則
本江邦夫
風景であれ、人物であれ、とにかく対象を描写することについて画家はほとんど疑いを持たない。持たないからこそ、「写生」と言う名目の下に克明な描写を仕上げて得意げであったりする。しかしながら、それはまずもって「虚心に見る」ことを前提としており、この前提を吟味しだすと今まで自明だったことがにわかに不分明になってくる。実際、自分が一個のレンズの眼をとおして見るかのように客観的に見据えているものが他人の目にも同じように映っているという確証は厳密にはどこにもないはずだ。また一口に見るといっても、ただうわべをなぞるのか、もっと本質的なものに迫ろうとするのか、その実態はけっして一様ではない。そういうこともあって、「写生」という言い方に集約される、世界ないし自然との真摯な対峙は今日的な課題とはなりえないようなのである。
ところが、石塚雅子の制作において、もっとも重要なのは、今や過去の遺物となりつつある、この「写生」という絶対的な態度なのだ。とはいっても、この誠実きわまりない画家にあってこうした極限的な段階がいきなり到来したわけではないことは注意を要する。真の写生を実現するためには、事象ないし対象にたいして、上辺だけでなく何面から迫ることが必要となる。今から思えば、石塚雅子の初期の作品、つまり大自然のエネルギーをそのまま求心的な渦巻きとしてとらえたかのような磁場とも重力場ともおぼしきヴィジョンはこうした内的な作業の結果ともいうべきものだ。画家自身のことばを借りれば、これらの厳粛なモノクロームの作品群は「目で見えているものではなく、世界に耳をすます中で自身の内側に深く刻まれたもの」をかたちとして呼び起こして描いたものなのである。それはいわば世界全体の内的な構造を直感的に把握するこころみだったといえようが、目に映るがままのイメージではけっしてなく、その意味でどこかしら観念的なところを感じさせるものであった。ふつうならば、こうした観念性は瑞々しい感性を欠いた硬直したものへと転落しかねないのだが、石塚の全体的な制作にあって、それはいわば感性の自由な展開を秩序づける基礎ないし枠組みとして機能することになる。こうした観念性というものがあってはじめて、画家は「見たものを見えたように描く」ことができるのである。
石塚雅子の新作は一見したところ黒を基調とする油絵具や木炭で白い背景にただ描きなぐっただけのように見える。しかし、人の感覚というのはじつに正確なもので、そうした線の混沌のなかにもある種の均衡と構造と根拠があることを瞬時にして察知するのである。それらはたんなる幻想の産物ではない。スケッチブックを手にして庭の草花と共に過ごした、ある親密で神秘的な時空の広がりの結実なのだ。だからこそ、見る者はそのまぶしいまでの線の饗宴のうちに、ただの造形的な戯れではない、なんらかの実質を感知するのだともいえよう。しかも、「一粒の砂に世界を、野花のうちに天国を見る」というブレイクの一節を引きつつ、この飾り気のない画家は言うのだ。「この世界や永遠について・・・美しい法則について考えます」と。本来の写生が暗黙の了解のうちに目指していたのは、この「美しい法則」の具現化であり、写真的な表層の事実ではないことを今いちど思い起こそう。
あるいは写生というものは超越的かつ変幻きわまりない世界と自然に到達するさいの通過儀礼にもひとしいものなのかもしれない。石塚雅子の次のような言葉はことさらに意味ぶかくきこえるのだ。「写生をすることで、私は少し謙虚になりました。画家は世界の美しさのしもべなのでしょう。私の描いた線や形が絵を見る人と世界を繋ぐものであればと思っています。」事実、ときに激しくときに繊細な画家の線描に誘われて見るものがそこに実現するのは、世界と自然の主体的な構築であり、このとき画家はシャーマンもさながらに、文字どおり芸術的仲介者として本質的な役割を果たすのである。
(もとえくにお 多摩美術大学教授・府中美術館長)
「遠心力/求心力」浦和と現代の美術 うらわ美術館 2001年
本江邦夫
風景であれ、人物であれ、とにかく対象を描写することについて画家はほとんど疑いを持たない。持たないからこそ、「写生」と言う名目の下に克明な描写を仕上げて得意げであったりする。しかしながら、それはまずもって「虚心に見る」ことを前提としており、この前提を吟味しだすと今まで自明だったことがにわかに不分明になってくる。実際、自分が一個のレンズの眼をとおして見るかのように客観的に見据えているものが他人の目にも同じように映っているという確証は厳密にはどこにもないはずだ。また一口に見るといっても、ただうわべをなぞるのか、もっと本質的なものに迫ろうとするのか、その実態はけっして一様ではない。そういうこともあって、「写生」という言い方に集約される、世界ないし自然との真摯な対峙は今日的な課題とはなりえないようなのである。
ところが、石塚雅子の制作において、もっとも重要なのは、今や過去の遺物となりつつある、この「写生」という絶対的な態度なのだ。とはいっても、この誠実きわまりない画家にあってこうした極限的な段階がいきなり到来したわけではないことは注意を要する。真の写生を実現するためには、事象ないし対象にたいして、上辺だけでなく何面から迫ることが必要となる。今から思えば、石塚雅子の初期の作品、つまり大自然のエネルギーをそのまま求心的な渦巻きとしてとらえたかのような磁場とも重力場ともおぼしきヴィジョンはこうした内的な作業の結果ともいうべきものだ。画家自身のことばを借りれば、これらの厳粛なモノクロームの作品群は「目で見えているものではなく、世界に耳をすます中で自身の内側に深く刻まれたもの」をかたちとして呼び起こして描いたものなのである。それはいわば世界全体の内的な構造を直感的に把握するこころみだったといえようが、目に映るがままのイメージではけっしてなく、その意味でどこかしら観念的なところを感じさせるものであった。ふつうならば、こうした観念性は瑞々しい感性を欠いた硬直したものへと転落しかねないのだが、石塚の全体的な制作にあって、それはいわば感性の自由な展開を秩序づける基礎ないし枠組みとして機能することになる。こうした観念性というものがあってはじめて、画家は「見たものを見えたように描く」ことができるのである。
石塚雅子の新作は一見したところ黒を基調とする油絵具や木炭で白い背景にただ描きなぐっただけのように見える。しかし、人の感覚というのはじつに正確なもので、そうした線の混沌のなかにもある種の均衡と構造と根拠があることを瞬時にして察知するのである。それらはたんなる幻想の産物ではない。スケッチブックを手にして庭の草花と共に過ごした、ある親密で神秘的な時空の広がりの結実なのだ。だからこそ、見る者はそのまぶしいまでの線の饗宴のうちに、ただの造形的な戯れではない、なんらかの実質を感知するのだともいえよう。しかも、「一粒の砂に世界を、野花のうちに天国を見る」というブレイクの一節を引きつつ、この飾り気のない画家は言うのだ。「この世界や永遠について・・・美しい法則について考えます」と。本来の写生が暗黙の了解のうちに目指していたのは、この「美しい法則」の具現化であり、写真的な表層の事実ではないことを今いちど思い起こそう。
あるいは写生というものは超越的かつ変幻きわまりない世界と自然に到達するさいの通過儀礼にもひとしいものなのかもしれない。石塚雅子の次のような言葉はことさらに意味ぶかくきこえるのだ。「写生をすることで、私は少し謙虚になりました。画家は世界の美しさのしもべなのでしょう。私の描いた線や形が絵を見る人と世界を繋ぐものであればと思っています。」事実、ときに激しくときに繊細な画家の線描に誘われて見るものがそこに実現するのは、世界と自然の主体的な構築であり、このとき画家はシャーマンもさながらに、文字どおり芸術的仲介者として本質的な役割を果たすのである。
(もとえくにお 多摩美術大学教授・府中美術館長)
「遠心力/求心力」浦和と現代の美術 うらわ美術館 2001年
2001年