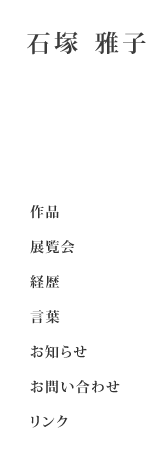■
庭の彼方に見えるもの
いけばな「龍生」2006年8月号
アトリエ訪問インタビュー
椿、雪柳、山吹、山茶花、萩。
そんな植物が自由に生い茂る“庭”に面したアトリエで、
彼女の手からいくつもの“庭”のシーンが描き出されていきます。
その風景の向こう側には一体、何が映し出されているのでしょうか。
繋がっていく“命”
部屋の花瓶に挿しておいた、百合の蕾。それを改めて描こうと思って、よく「見て」みると、“命”の流れが感じられました。そして部屋中を満たす、熟れたような香りも「生きている!」と主張しているように思えたのです。百合に見た形だけでなく、その内側から出てくるエネルギーを描きたい、そう思いました。そして、凝縮されたエネルギーを感じたしべから描き始めて、花弁へ。モチーフである百合を密に「見」ながら描くことで植物から何かを感じ、自ずと描く線に緩急がついたり、曲がったりしていきました。
そうして、植物自体を描いていくうちに、その周りを含めた風景も描くようになりました。植物と直に向き合うところから離れてみて、自分とちょっと距離を置いて接してみようと思ったのです。それが、自分の家の“庭”でした。そこには様々な植物が育っていて、光や陰、空、風といった、いろいろな要素があり、自分との距離が生まれたことで、様々な関係の中での植物の表情が見えてきました。例えば、木漏れ日が差し、きらきらと輝く葉と、その陰になった葉の黒とのコントラスト。台風で、激しく揺れる木々たち。そして庭の中に育つ一本の萩の木にしても、枯れて、気が付けば、再び次の年には同じ場所から生えてくる。そこでは、「植物単体」よりももっと広い、植物を含んだ“庭”全体のエネルギーや関係、そしてそこに織り込まれていく生命の循環までも感じられる気がしたんです。
空を描いた作品を見て、日本海沿岸で生まれた、ある人が、故郷の日本海の海や空を感じた、と言ってくれたことがありました。そんなふうに、その人が作品に見ているものと、私の見ている庭や風景と違ってもいいんです。私が捉えたものが、その人の中に潜んでいた思い出を喚起するようなものであればいい、そう思っています。
(石塚雅子/談)
プランツ・プランツ・ギャラリー19
いけばな「龍生」2006年8月号
アトリエ訪問インタビュー
椿、雪柳、山吹、山茶花、萩。
そんな植物が自由に生い茂る“庭”に面したアトリエで、
彼女の手からいくつもの“庭”のシーンが描き出されていきます。
その風景の向こう側には一体、何が映し出されているのでしょうか。
繋がっていく“命”
部屋の花瓶に挿しておいた、百合の蕾。それを改めて描こうと思って、よく「見て」みると、“命”の流れが感じられました。そして部屋中を満たす、熟れたような香りも「生きている!」と主張しているように思えたのです。百合に見た形だけでなく、その内側から出てくるエネルギーを描きたい、そう思いました。そして、凝縮されたエネルギーを感じたしべから描き始めて、花弁へ。モチーフである百合を密に「見」ながら描くことで植物から何かを感じ、自ずと描く線に緩急がついたり、曲がったりしていきました。
そうして、植物自体を描いていくうちに、その周りを含めた風景も描くようになりました。植物と直に向き合うところから離れてみて、自分とちょっと距離を置いて接してみようと思ったのです。それが、自分の家の“庭”でした。そこには様々な植物が育っていて、光や陰、空、風といった、いろいろな要素があり、自分との距離が生まれたことで、様々な関係の中での植物の表情が見えてきました。例えば、木漏れ日が差し、きらきらと輝く葉と、その陰になった葉の黒とのコントラスト。台風で、激しく揺れる木々たち。そして庭の中に育つ一本の萩の木にしても、枯れて、気が付けば、再び次の年には同じ場所から生えてくる。そこでは、「植物単体」よりももっと広い、植物を含んだ“庭”全体のエネルギーや関係、そしてそこに織り込まれていく生命の循環までも感じられる気がしたんです。
空を描いた作品を見て、日本海沿岸で生まれた、ある人が、故郷の日本海の海や空を感じた、と言ってくれたことがありました。そんなふうに、その人が作品に見ているものと、私の見ている庭や風景と違ってもいいんです。私が捉えたものが、その人の中に潜んでいた思い出を喚起するようなものであればいい、そう思っています。
(石塚雅子/談)
プランツ・プランツ・ギャラリー19
2006年